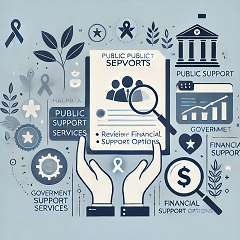デジタル遺産が法律トラブルに?相続税やプライバシーの盲点
近年、デジタル遺産の管理が注目されていますが、その背後には見過ごされがちな法律トラブルのリスクが潜んでいます。相続税の計算やプライバシー侵害の可能性など、適切な対策を講じなければ、死後に家族や相続人を悩ませる事態になるかもしれません。
見落とされがちな相続税の問題
デジタル遺産とは、SNSアカウント、オンラインバンク、仮想通貨、クラウドデータなど、個人がインターネット上で持つあらゆる資産を指します。これらの中でも特に仮想通貨やNFT(非代替性トークン)は、相続税の対象となる可能性が高い資産です。
問題は、その評価額や申告方法が不透明である点です。仮想通貨は価格変動が激しく、評価時期を間違えると過剰な税負担を招きかねません。また、デジタル遺産の存在自体を知らなければ、相続人が税務署から申告漏れを指摘されるリスクもあります。知らない間に罰則が科されることを避けるためにも、生前に遺産のリストアップが不可欠です。
プライバシー侵害のリスクとは?
死後のデジタル遺産は、相続人がアクセスする際にプライバシーの侵害問題を引き起こすことがあります。メールやSNSメッセージの中には、第三者の個人情報や秘密が含まれている場合があります。相続人がそれを意図せず閲覧することで、トラブルに発展することも少なくありません。
さらに、SNSやクラウドサービスの利用規約によっては、アカウントやデータが相続の対象外となる場合があります。この場合、相続人が管理を試みると法的な問題を引き起こす可能性も。アカウント削除やデータ移行の際は、必ず法的な手続きを確認する必要があります。
生前対策が鍵を握る
これらの問題を回避するためには、デジタル遺産を専門に扱う法律家や行政書士のサポートを受け、生前に遺産リストや意思表示を明確にしておくことが重要です。また、仮想通貨やNFTなどの資産については、取引履歴や秘密鍵の管理方法を家族に伝える工夫が必要です。
デジタル遺産は便利さとリスクが表裏一体の存在。今こそ、その盲点に目を向け、死後のトラブルを未然に防ぐ一歩を踏み出しましょう。家族の負担を軽減するためにも、「放置」ではなく「対策」を選ぶことが未来の安心につながります。
ご相談・お問い合わせはこちらから
お問い合わせフォーム